

物販やせどりで中古品を扱う際、多くの人が「古物商許可」の取得を検討します。
しかし、「自分に本当に必要なのか」「取り方が難しそう」といった疑問を持つ方も少なくありません。
この記事では、古物商許可の基本から、個人・法人別の具体的な取り方、申請手順、必要書類までを分かりやすく解説します。


物販やせどりで中古品を扱う際、多くの人が「古物商許可」の取得を検討します。
しかし、「自分に本当に必要なのか」「取り方が難しそう」といった疑問を持つ方も少なくありません。
この記事では、古物商許可の基本から、個人・法人別の具体的な取り方、申請手順、必要書類までを分かりやすく解説します。
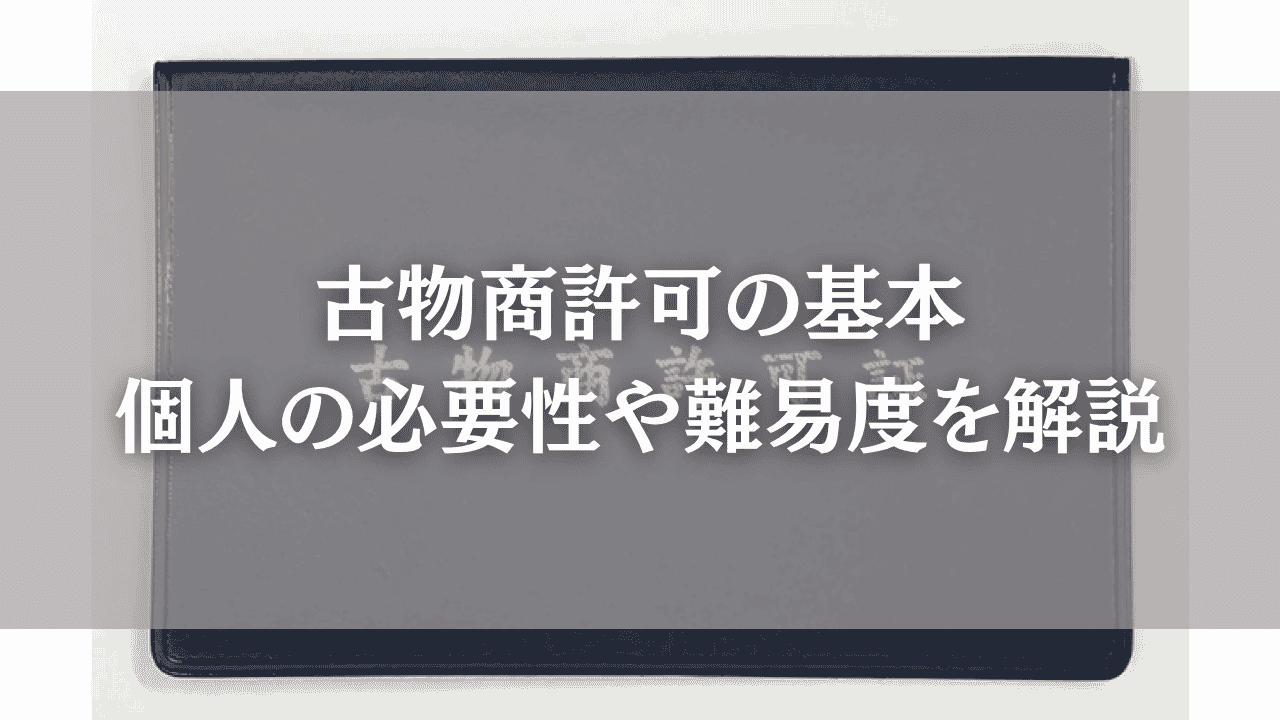


古物商許可は、物販やせどりを行う上で非常に重要な制度です。
ここでは、許可の基本的な意味や、個人の必要性、難易度について解説します。

古物商許可とは、ビジネスとして中古品(古物)を売買するために必要な、警察署経由で申請する許可証のことです。
この制度は、盗品が市場に出回るのを防ぎ、犯罪を防止する目的で設けられています。
そのため、中古品を仕入れて販売する「せどり」や「リサイクルショップ」などの物販事業者は、法律に基づきこの許可を取得するよう定められています。

古物商は「資格」ではなく「許可」であり、取得にあたって筆記試験や面接などは一切ありません。
一般的な資格試験とは異なり、法律で定められた要件(欠格事由に該当しないことなど)を満たして申請すれば、原則として許可されます。
難易度を心配する必要はなく、あくまで行政手続きの一環と捉えて問題ないでしょう。

古物商許可は、法人だけでなく個人(個人事業主)でも問題なく取得できます。
実際に、副業やスモールスタートで物販を始める個人の多くが、この許可を取得しています。後ほど詳しく解説しますが、個人と法人では申請時に必要な書類が一部異なる点を押さえておきましょう。

「利益を出す目的で、中古品を仕入れて転売する」場合は、古物商許可が必要です。
売上がいくら以上といった金額の基準ではなく、「利益目的の仕入れ行為」が1回でもあれば対象となります。
具体的には、以下のようなケースです。
逆に、以下のような「不要なケース」も存在します。
判断基準は「不用品の処分」か、「利益目的の仕入れ転売」か、という点になります。
メルカリやヤフオクなどのiPhoneを使ったフリマアプリでも、
「利益目的の仕入れ」を行うなら許可は必須です。
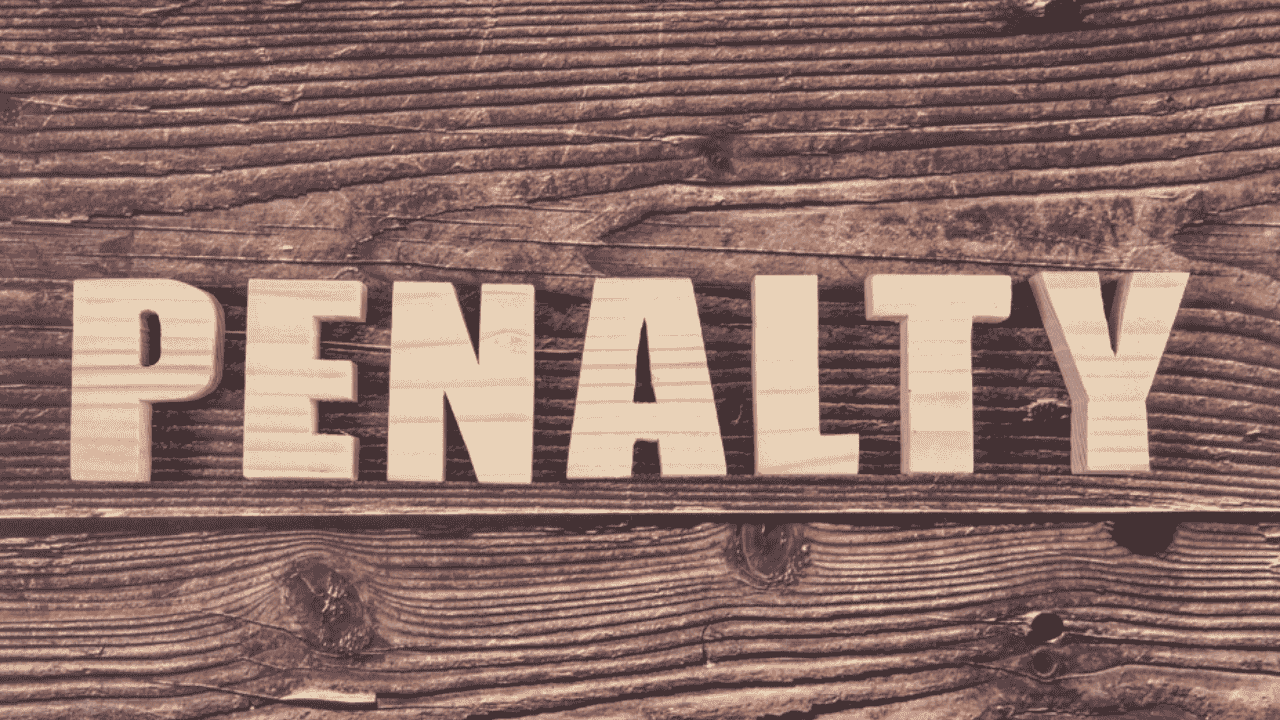
古物商許可を持たずに無許可で営業した場合、重い処罰が科されるリスクがあります。
具体的には、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります(古物営業法第31条)。
物販やせどりを安心して続けるためにも、中古品を扱う場合は必ず事前に許可を取得しましょう。

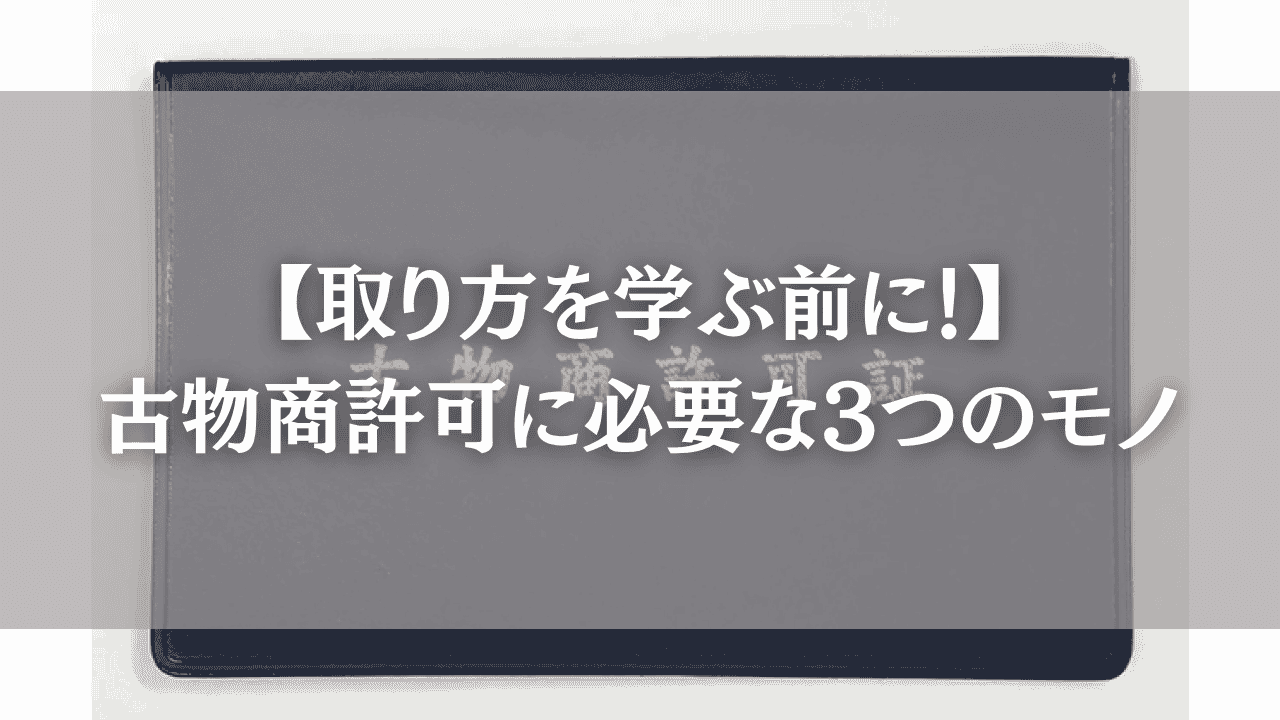


古物商許可の申請には、具体的な「取り方」のステップに進む前に、必ず満たしておくべき3つの準備すべきモノ(条件)があります。
これらが準備できていないと申請自体が受理されないため、事前にしっかり確認しましょう。

古物商の許可を得るには、営業活動の拠点となる「営業所」が必ず必要です。
「営業所」とは、古物の売買や管理を実際に行う物理的な場所を指します。
たとえインターネット(iPhoneなどを使ったフリマアプリ)のみで取引を行う場合でも、商品の管理や事務作業を行う場所として設定しなくてはなりません。
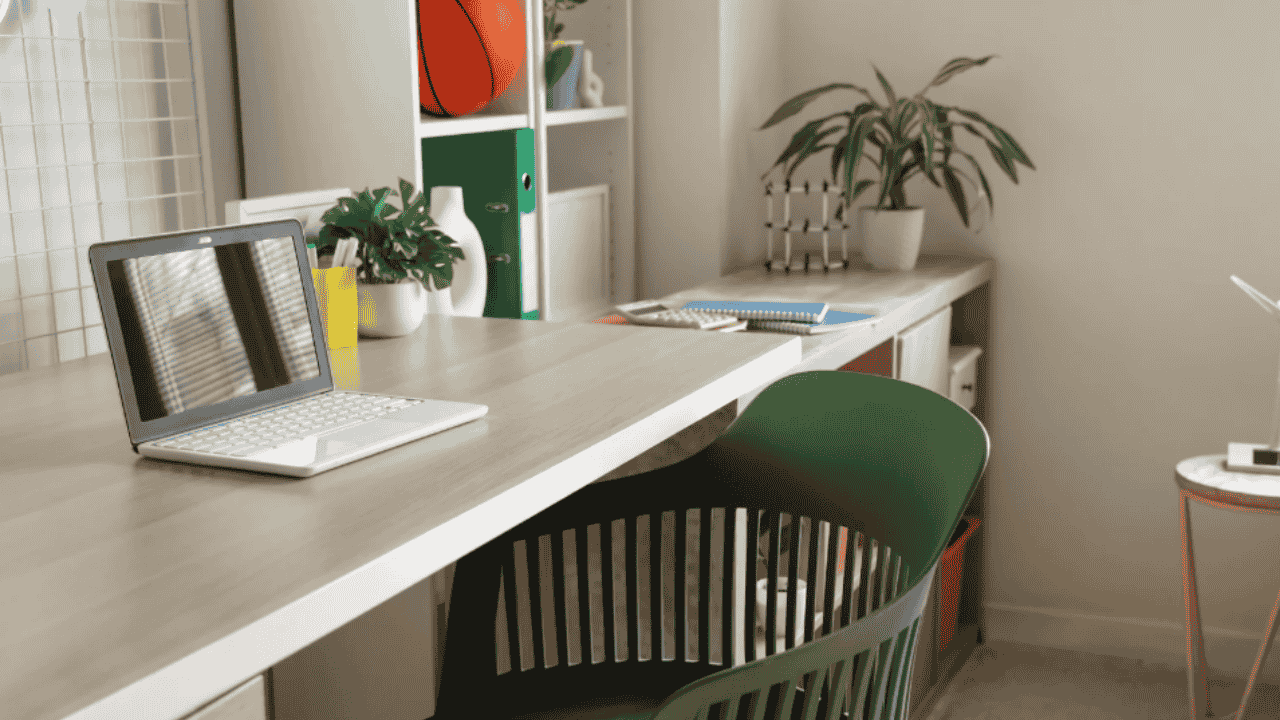
結論として、自宅や賃貸アパートを営業所として申請することは可能です。
ただし、いくつかの条件を満たす必要があります。

古物商の営業所には、必ず1名の「管理者」を決めておく必要があります。
このプロセスを「管理者の選任(せんにん)」と呼びます。管理者は、その営業所における古物取引が法律に沿って適正に行われるよう監督する責任者です。
特別な資格は不要で、個人事業主の場合は申請者本人が管理者を兼任するのが一般的です。
申請者(法人の場合は役員含む)と管理者は、「欠格事由(けっかくじゆう)」という条件に当てはまらないことが必要です。
欠格事由とは、法律で定められた「許可を与えるのにふさわしくない条件」のことです。
主な欠格事由には以下のようなものがあります。
これらに一つでも該当する場合、残念ながら許可が下りることはありません。

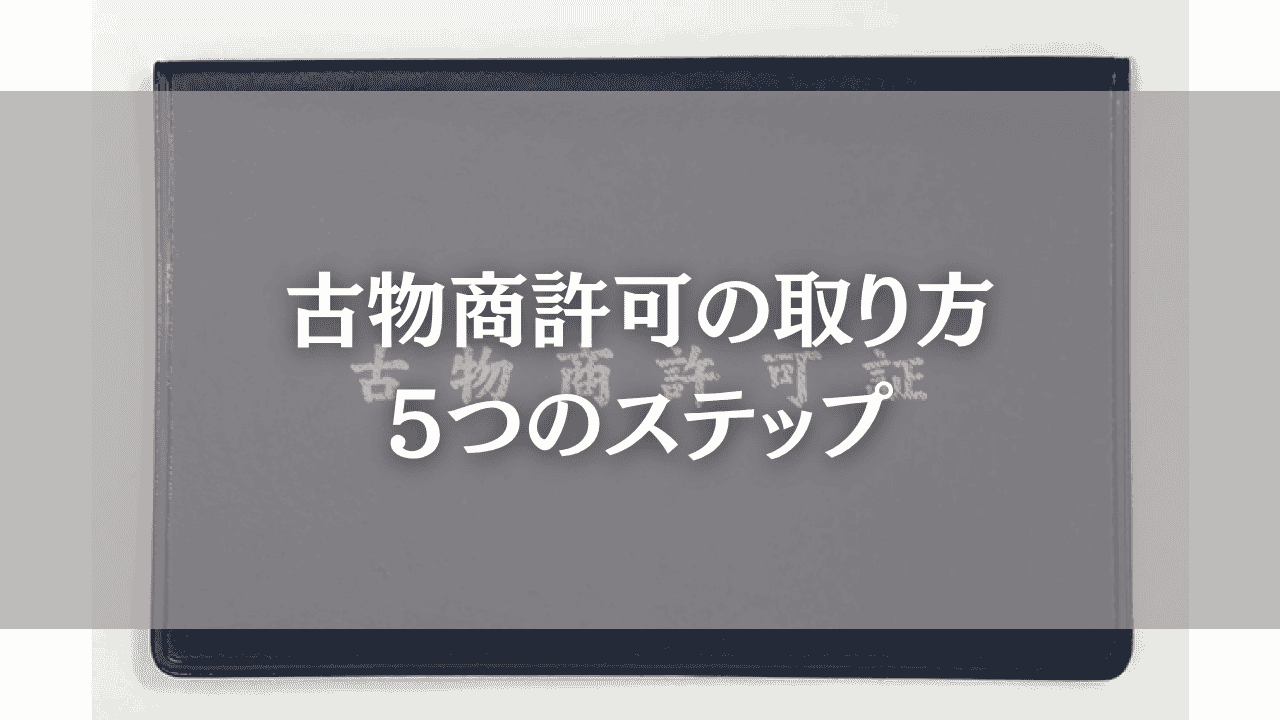
助手:「博士、許可を取るための具体的な手順を教えてください!」 博士:「うむ。慌てず焦らず、この5つのステップで進めるのが確実じゃ。」


古物商許可の申請は、手順さえ理解すれば個人でも十分可能です。
ここでは、申請から許可証交付までの流れを5つのステップに分けて解説します。
申請の第一歩は、営業所を管轄する警察署の「生活安全課 防犯係」へ事前相談に行くことです。
なぜなら、申請に必要な書類や要件は全国一律の部分と、各都道府県の警察(公安委員会)が定めるローカルルールが混在しているためです。
最初に相談することで、二度手間や書類不備を防ぐことができます。
相談の際は、以下の点を伝えるとスムーズです。
担当者が不在の場合もあるため、事前に電話でアポイントを取っておくとよいでしょう。
警察署で確認したリストに基づき、必要な書類を収集します。
書類には、大きく分けて以下の3種類があります。
住民票や身分証明書などの公的書類は、「発行から3ヶ月以内」といった有効期限が定められている場合がほとんどです。
申請直前にまとめて取得することをおすすめします。
警察署の窓口や各都道府県警のウェブサイトから「古物商許可申請書」の様式(ExcelやPDF)を入手し、作成します。
警察署の窓口で配布されている記入例や、ウェブサイトの見本を参考にしながら、正確に記入してください。
書き方が分からない箇所は空欄にしておき、提出時に窓口で質問しながら記入する方が確実です。
申請書は複数枚にわたるため、記入ミスや押印漏れがないよう、提出前にしっかり確認しましょう。
すべての書類が揃ったら、管轄の警察署の窓口で申請手続きを行います。
申請時には、手数料として19,000円が必要です。この費用は、許可が下りなかった場合(不許可)でも返金されません。
手数料の納付方法は、窓口での現金払い、収入証紙の購入など、都道府県によって異なります。あらかじめ相談の際に確認しておきましょう。書類に不備がなければ、ここで正式に受理されます。
申請が受理されると、都道府県公安委員会による審査が開始されます。
審査では、申請者が欠格事由に該当していないか、営業所が適切かなどがチェックされます。
審査期間の目安は、標準処理期間として「受理から40日(土日祝除く)」とされていますが、混雑状況などにより前後することがあります。
審査が完了し、許可が下りると警察署から電話などで連絡が入ります。指定された日時に警察署へ赴き、古物商許可証を受け取れば、すべての手続きは完了です。
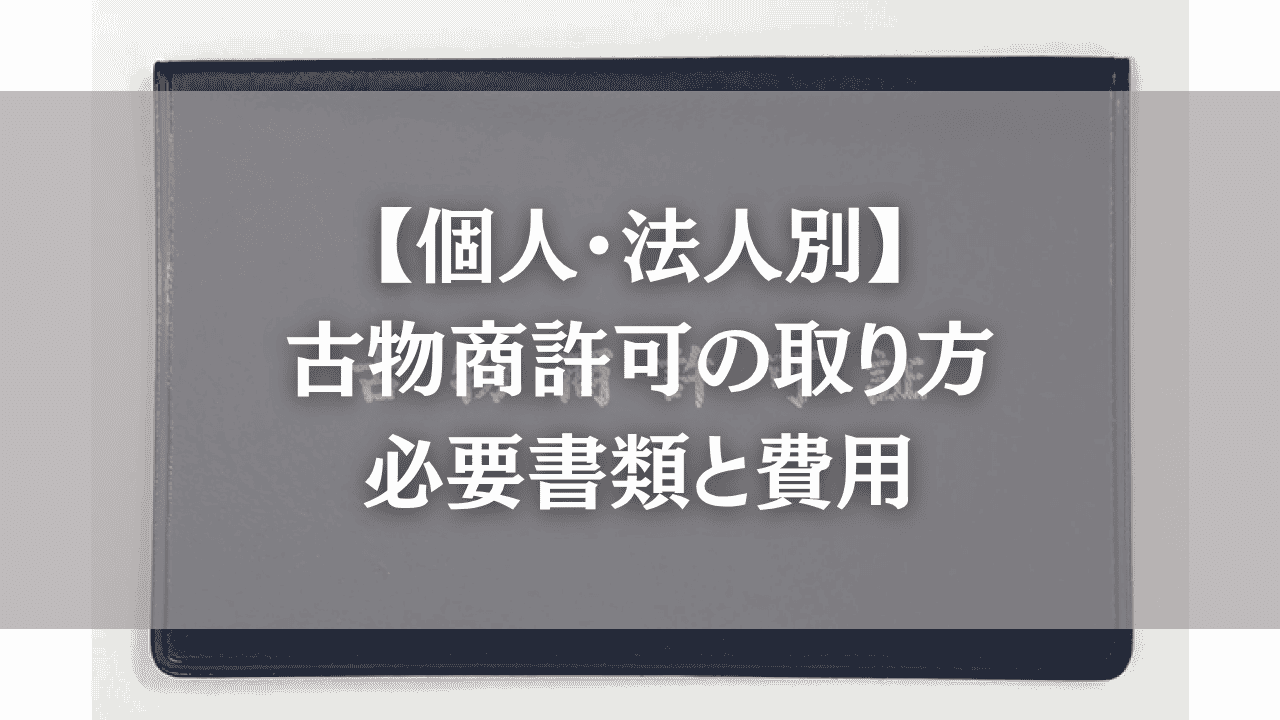


古物商許可の申請は、個人か法人かによって必要書類が大きく異なります。
ここでは、それぞれのケースで必要な書類一覧と、総額の費用や期間を解説します。
個人の古物商許可申請では、主に申請者本人と管理者の身元を証明する書類が必要です。
申請する警察署によって若干の違いがあるため、必ず事前に管轄の警察署へ確認しましょう。一般的に必要となる書類は以下の通りです。
警察署の窓口で受け取るか、各都道府県警のホームページからダウンロードできます。
直近5年間の職歴や学歴などを記載します。様式は警察のホームページで入手可能です。
「欠格事由に該当しない」ことを誓約する書類です。これも警察のホームページで入手できます。
「本籍地(外国籍の方は国籍等)」が記載されており、マイナンバーが記載されていないものが必要です。お住まいの市区町村役場で取得します。
運転免許証や保険証のことではありません。「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことを証明する書類で、本籍地の市区町村役場で取得します。
ホームページを開設する場合はそのURLを登録する権限があることを示す書類が必要です。
法人申請の場合は、個人の書類に加えて、会社の登記に関する書類と「役員全員分」の書類が必要になります。
準備に時間がかかるため、個人の申請よりも余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。
個人と同様に必要です。
法務局で取得できます。会社の目的(事業内容)に「古物営業」に関連する文言が含まれているか確認が必要です。
コピーに「原本と相違ありません」といった奥書と、代表者の署名・押印が必要です。
法人の場合、代表取締役を含む「役員全員」の略歴書が必要です。
略歴書と同様に、「役員全員」分が必要です。
役員全員分の「本籍地」記載かつマイナンバー不記載のものが必要です。
役員全員分の「本籍地」で取得する身分証明書が必要です。
古物商許可の申請自体にかかる法定手数料は、全国一律で19,000円です。
この手数料は、申請時に警察署の窓口で支払います。万が一、審査に落ちて不許可となった場合でも、この19,000円は返金されません。
また、法定手数料とは別に、各種証明書を取得するための実費が数千円程度かかります。
| 項目 | 費用目安(1人あたり) | 取得場所 |
| 住民票の写し | 300円程度 | 市区町村役場 |
| 身分証明書 | 300円程度 | 本籍地の市区町村役場 |
| 登記事項証明書(法人のみ) | 600円程度 | 法務局 |
| 合計(個人) | 1,000円〜2,000円程度 | - |
| 合計(法人) | 役員の人数により変動 | - |
個人の取り方であれば総額2万円程度、法人の場合は役員の人数分の証明書費用が加算されると考えておくとよいでしょう。
警察署に申請書類を提出してから許可証が交付されるまでの標準的な審査期間は、約40日です。
これはあくまで目安であり、土日祝日や年末年始は含まれません。そのため、実際には1ヶ月半から2ヶ月程度かかると想定しておきましょう。
書類の不備があれば、さらに期間が延びてしまいます。物販やせどりの開始スケジュールが決まっている方は、できるだけ早く「取り方」の準備を始めることをおすすめします。
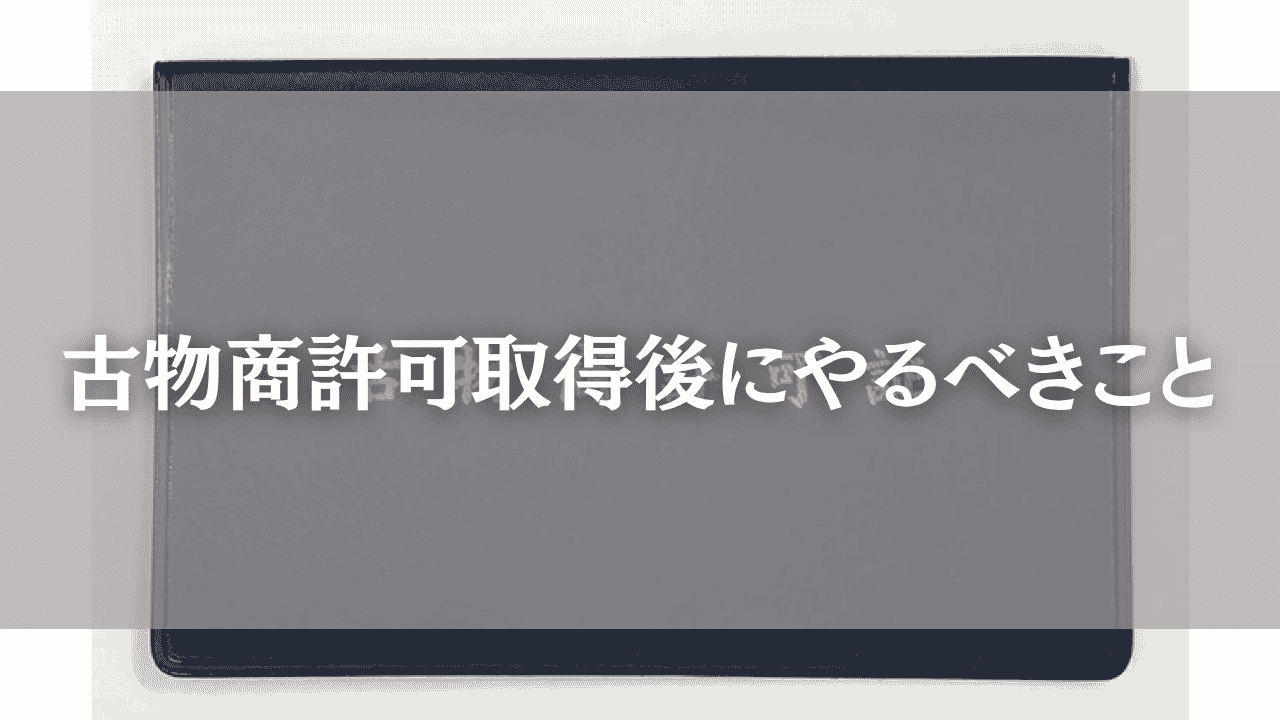


古物商許可は、許可証を受け取ったら終わりではありません。
営業を開始するために必要なプレートの掲示や、ネット販売を行うための届出など、許可後に対応すべき手続きを確認しましょう。
許可証を受け取ったら、まず「古物商プレート」を作成し営業所に掲示する必要があります。
古物商プレート(標識)は、営業所の見やすい場所に掲示することが古物営業法で義務付けられています。
許可証の交付連絡があった際に、警察署で様式(サイズや記載内容)の指示を受け、専門の業者に発注するのが一般的です。
自身のWebサイトやECサイトで古物売買を行う場合は、そのURLを警察署に届け出る必要があります。
この届出は、許可申請時に同時に行うことも、許可取得後に「変更届出」として提出することも可能です。
メルカリやヤフオクなどのモール型サイトへの出店(自分のストアページを持つ場合)も対象となるため、ネット販売を考えている方は必ず対応しましょう。
URLの届出を行う際は、「URL疎明資料」の提出を求められます。
URL疎明資料とは、申請者がそのURLを使用する権限を持っていることを証明する書類です。一般的には、ドメインの登録情報(Whois情報)が確認できる画面のキャプチャや、プロバイダから送付された契約内容通知書などが該当します。
URL疎明資料は、スマートフォン(iPhoneなど)からでも準備が可能です。
例えば、iPhoneの標準ブラウザであるSafariを使用してドメイン管理会社のマイページにログインし、契約者情報やドメイン情報が記載されたページを表示させます。
その画面のスクリーンショットを撮影し、印刷することで疎明資料として利用できる場合があります。
古物商許可証には、自動車免許のような定期的な更新制度や有効期限はありません。
一度取得すれば、原則として生涯有効です。ただし、営業を6ヶ月以上休止する場合や、廃業する場合には返納届が必要となるため注意しましょう。
許可証に記載されている氏名や住所、法人の名称や所在地などに変更があった場合は、変更届出が必要です。
これらの変更は、事後(変更から14日以内)の届出で問題ありませんが、手数料(1,500円)のかかる「書換申請」が必要となります。引っ越しや結婚などで変更が発生した際は、速やかに管轄の警察署に相談しましょう。


物販で利益(所得)が出た場合、会社員の方でも副業の所得が年間20万円を超えると「確定申告」が必要になります。
でも、「やり方が分からない」「間違えたらペナルティがあるかも…」と不安に感じる方も多いですよね。
特に物販特有の会計ルールは、一般的な情報だけでは分かりにくいもの。
そこで今回は、そんな確定申告の悩みを解決する決定版とも言える講座をご紹介します。
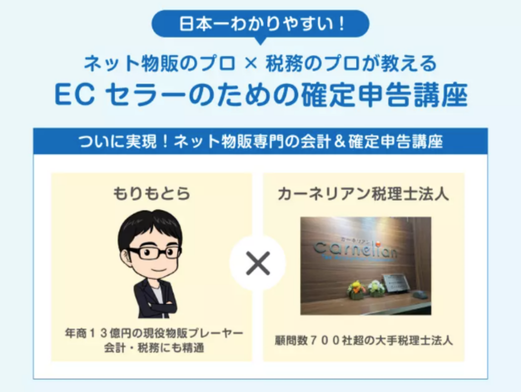
この講座の最大の特徴は、年商13億円超の現役トップ物販プレイヤー「もりもとら」さんと、顧問数700社超の大手税理士法人「カーネリアン税理士法人」がタッグを組んで作成している点です。
もしあなたが、
と感じているなら、この講座がきっと役立ちます。
一般的な税金の本には載っていない、ネットで販売する方が本当に知りたい会計処理を初心者にも分かりやすく解説。
税務調査で慌てないための守りの知識がしっかり身につきます。
大きな失敗をしてしまう前に、この講座で「正しい税金の知識」を身につけて、安心してビジネスを続けられるようにしませんか?
ネット物販を安全に、そして長く続けるために知っておきたい知識が詰まっています。ぜひ詳細を確認してみてくださいね。
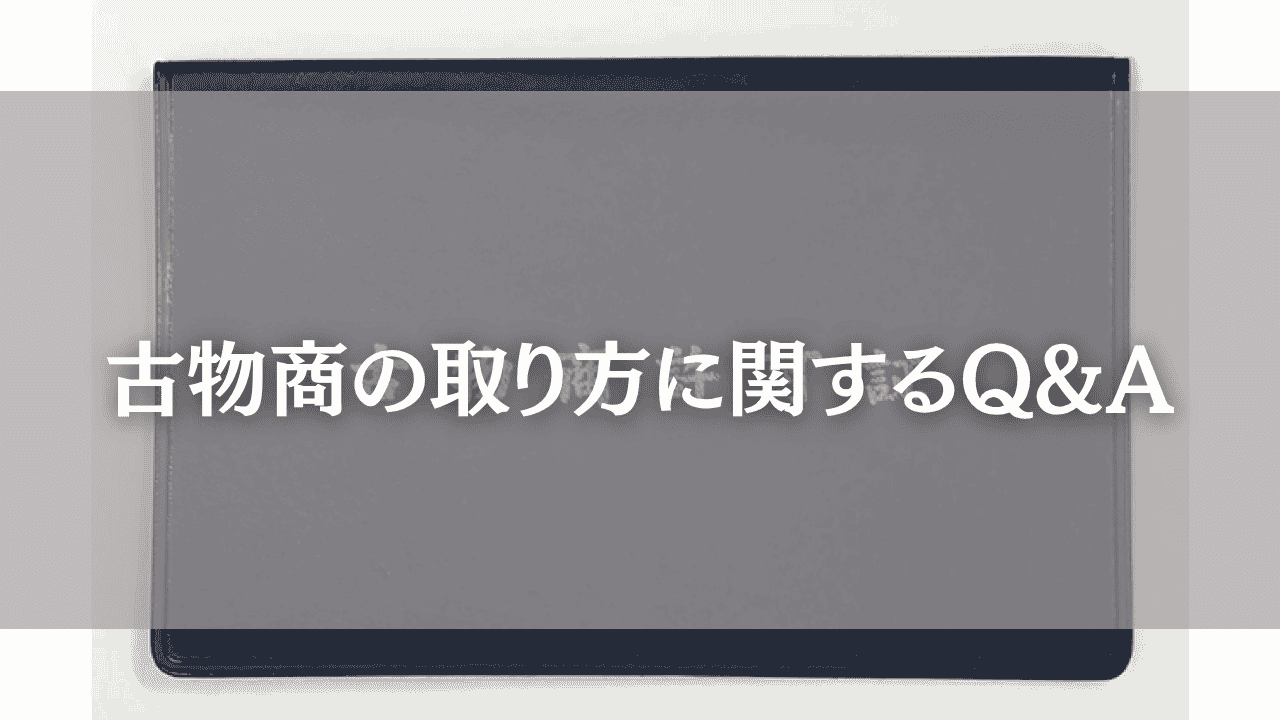
古物商許可の申請に関して、よく寄せられる質問と回答をまとめました。
A: 許可取得が直接バレることは稀です。
警察署から会社へ許可取得の通知が行くことはありません。ただし、副業の所得が増えて住民税が変動したり、ネット販売のURL届出情報(公表を選択した場合)などから、会社に知られる可能性はゼロではありません。
A: 書類さえ揃えれば難しくありません。
先に解説した通り、古物商は試験のない「許可」です。必要な要件を満たし、不備のない書類を提出すれば、個人でも問題なく取得できます。ただし、平日に役所や法務局を回るなど、書類収集の手間はかかると言えるでしょう。
A: 欠格事由に該当すると落ちます。
先に解説した「欠格事由」(特定の犯罪歴がある、住所不定である等)に該当する場合や、営業所の実態が確認できない場合、申請書類に虚偽があった場合は不許可となります。不安な点は、必ず申請前の「事前相談」で警察署に確認しましょう。
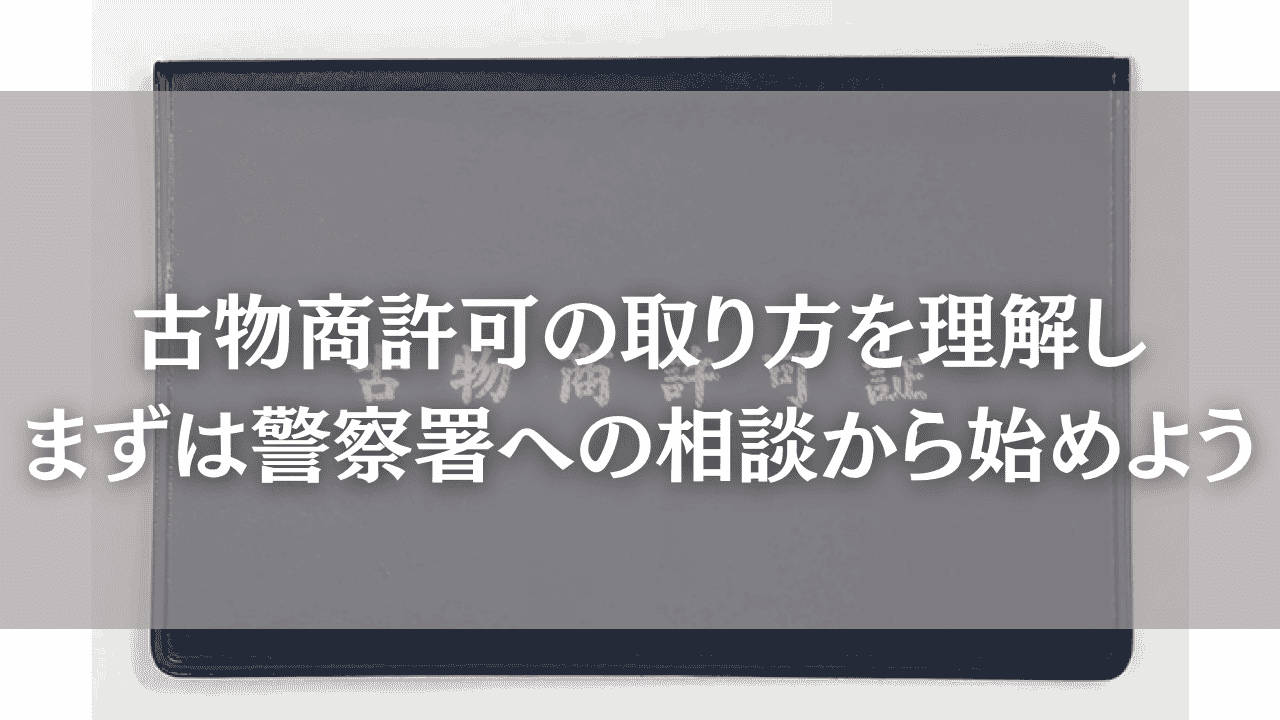


古物商許可の取得は、せどりや物販ビジネスを適法に行うための第一歩です。
一見、書類集めや手続きが複雑に感じるかもしれませんが、解説したステップや要件を一つずつ確認すれば、個人でも自分で申請することは十分に可能です。
必要な準備を整え、まずは営業所を管轄する警察署の窓口で「事前相談」をしてみることから始めてみましょう。
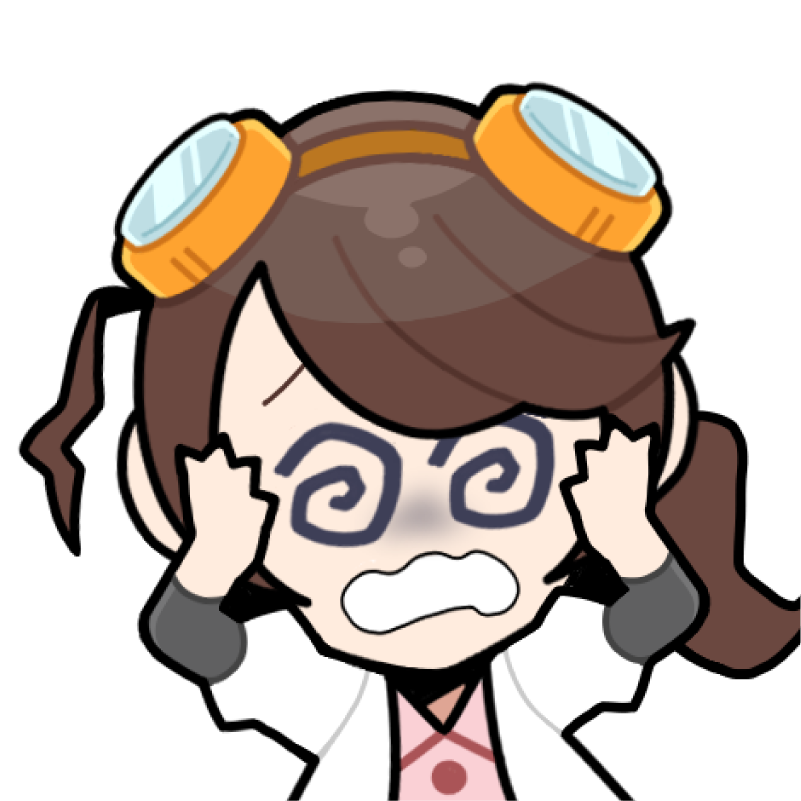



| 初心者おすすめ度 | ★★★☆☆ |
| 即金性 | ★★★☆☆ |
| ビジネス継続性 | ★★★★★ |
| 仕入れに必要な資金目安 | 5万円~ |
| 目指せる利益額 | 50万円以上 |

せどりからのNEXTステップにはおすすめ!
せどりで伸び悩んでいる、限界を感じる人は問屋仕入れで仕組み化を目指そう!
問屋開拓までの忍耐力は必要だけど、基本的にリピート仕入れで完結するので、せどりのように、掘り出し物を探すのに頭を悩ませる必要は無くなります。

コメント